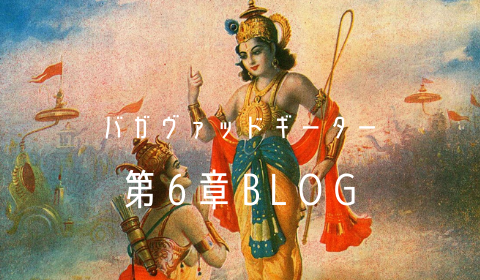
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।
yatroparamate cittaṃ niruddhaṃ yogasevayā |
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥६.२०॥
yatra caivātmanātmānaṃ paśyannātmani tuṣyati ||6.20||
瞑想の実践によって制御された心が(アートマーに)とどまり
自分自身のみにより、自分自身を見て、自分自身に喜ぶとき...
-
この詩のアートマーは、サット・チット・アーナンダ・アートマーを指し、自分自身をブランマンと認識していることを意味します。
考えによって[アートマナー]、つまりヴルッティで、自分自身をブランマンと認識し、自分自身の中に喜びます[アートマニ トゥッシャティ]。
この詩では、アートマーに3つの格の語尾が使われています。
第2格は、目的格「自分自身を[アートマーナム]」
第3格は、具格「自分自身によって[アートマナー]」
第7格は、所格「自分自身の中に[アートマニ]」
ヨーギーである、自分自身[アートマー]が、第1格の主格で、喜びの行い手です。
自分自身によって、自分自身を見て、自分自身の中に喜びます[アートマーナー アートマーナム パッシャン アートマニ トゥッシャティ]。
アートマーの本質は、足りていないという感覚から自由ですから[アーナンダ]、その人は、アートマーの中に喜びます。
