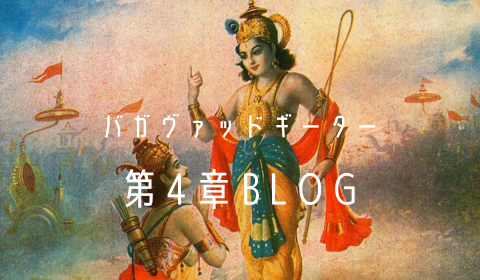
चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥४.१३॥
cāturvaṇyaṃ mayā sṛṣṭaṃ guṇakarmavibhāgaśaḥ |
tasya kartāramapi māṃ viddhyakartāramavyayam ||4.13||
(人々の)4つのグループ分け、義務や資質に基づいた分類が私によって作られました。私がその作者ですが、私は行い手ではなく、決して変わらないものであると知りなさい。
-
この詩は、クリシュナが人々を4つのグループに分けるヴェーダの体系に言及し、自身がその創造主[kartā]でありながら、同時に、行い手ではない[a-kartā]と、一見矛盾した概念について説明しています。
クリシュナは、自身が万物の創造主であり、人々を4つのグループに分けたと語ります。
これはインドに限定されず、普遍的に適用できる概念です。
社会には常に、王族、貴族、富裕層、貧困層、そして上流階級、下流階級といった分類が存在するからです。
ヴェーダの教えでは、この分類は個人の資質[guṇa]と義務[karma]に基づいています。
クリシュナは、自身をこの4つのグループ分けの作者[kartā]であると同時に、行い手ではない[a-kartā]とも述べています。彼は、自身が、不変[avyaya]であり、いかなる変化も受けないため、「a-kartā」であると説明します。
この一見矛盾する声明は、以下の2つの点を考察することで理解できるとしています。
1.グナとカルマ(資質と義務)に基づく人々のグループ分けの理解。
2.イーシュヴァラがどのようにして「行い手(kartā)」でありながら、同時に「行い手ではない(a-kartā)」のかという概念の解明。
この詩は、これらの点を掘り下げています。
◎グナの性質
すべての人は、サットヴァ、ラジャス、タマスという3つの質を併せ持っています。
これらのグナの優劣によって、以下の4つの主要な組み合わせが生まれ、これが人々を4つのグループに分ける基盤となります。
1.サットヴァ-ラジャス-タマス: 熟考、探求、平穏、規律といったサットヴァな特性が目立ちます。
2.ラジャス-サットヴァ-タマス: 規律を持ちつつも、大きな野心、エネルギー、熱意といったラジャスな特性が際立ちます。
3.ラジャス-タマス-サットヴァ: ラジャスが優勢でありながら、タマスな要素も強く影響します。
4.タマス-ラジャス-サットヴァ: 鈍さ、倦怠感、怠惰といったタマスな特性が優勢です。
これらの組み合わせは固定されたものではなく、人生の段階や状況によって変化すると説明されています。
例えば、乳児期にはタマスが優勢で睡眠が多いですが、成長と共にラジャスが優勢になり活発になり、最終的にはサットヴァ性質[sātvika]を持つことが期待されます。
◎気質に従う人々の4つのグループ [guṇa-vibhāga]
1.サットヴァ-ラジャス-タマス
サットヴァが優位で、深く考えることを好み、人生の根本的な価値や目的を探求します。
情緒的に成熟しており、探求者や哲学者としての傾向が強く見られます。
2.ラジャス-サットヴァ-タマス
ラジャスが優位で非常に活動的ですが、その野心は他者の福祉や特定の理想に向けられます。行動が思考[sattva]によって裏付けられているため、優れたリーダーシップを発揮し、他者への配慮、生命、富、自由を尊重します。
3.ラジャス-タマス-サットヴァ
ラジャスが優位ですが、思考よりも野心が先行します。他者への配慮を欠き、金銭や権力などを追求しがちです。サットヴァの側面も持つため知的ではありますが、タマスが優位であるため、策略、操作、他者搾取といった行動が多く見られます。ダルマを軽視し、自己の野心を最優先するため、独裁者になる可能性もあります。犯罪者から単に自己中心的なセールスマンまで、幅広い行動パターンがあります。
4.タマス-ラジャス-サットヴァ
タマスが優位なため、やる気がなく、野心もほとんどありません。最悪の場合、小規模な犯罪者となるか、良くても単調な業務をこなす従業員にとどまります。自身の怠惰を正当化し、目標があってもそれを達成するための努力を避ける傾向があります。
タイプ4の人が、タイプ1のような成熟した状態になるためには、段階的な成長が必要であり、タイプ2、次にタイプ3を経由する必要があります。
このプロセスは「成長」や「成熟」と呼ばれ、カルマ・ヨーガの実践によって可能です。
タイプ3までは、ダルマに従って目的を追い求めながら行いをすることで成熟が進みます。
しかし、真の成熟、つまりタイプ1に到達しサンニャーシーとなるのは、カルマ・ヨーガの態度でカルマを行うときだけです。
タイプ2に到達すれば、価値観が明確になるため、自動的にダルマに従うようになります。
◎4つの側面をもった分け方の不変性
サットヴァ、ラジャス、タマスという3つの性質が、インドだけでなく全世界の人々のグループに違いを生み出しています。
これらの性質は唯一バガヴァーンに属するものであり、この性質[prakṛti]に基づいて、人々の習性による分類[guṇa -vibhāga]がなされます。
誰もが4つの構成を通して、成熟するため、すべての人は3つのグナの配列で形成される4つのグループに分類されます。
これが、この詩で言及されている、習性に基づくの4つの分類[guṇa -vibhāga]です。
◎義務を基にした人々の分類
この体系にはもう1つ、役割に基づく分類[karma-vibhāga]があります。
1.ブラーンマナの役割
教えること、儀式を執り行うこと、社会の幸せのために祈ること、そして質素に暮らすことが主な役割です。自己を律し、ヴェーダを学び、聖職者として人々のために奉仕します。
2.クシャトリヤの役割
ダルマを守り、人々を統治し、防衛、行政、司法、法執行を担います。社会秩序の維持と保護がその役割です。
3.ヴァイシャの役割
商業、農業、牧畜など、物資の生産と供給を担います。社会に経済的基盤を提供し、流通を支える役割です。
4.シュードラの役割:
他の3つの役割を果たす人々への奉仕が主な役割です。彼らの活動がなければ、社会の機能は成り立ちません。
これらの役割は、単なる家柄や生まれによって決まるものではなく、本来は個人の性質[guṇa]に基づくと述べられています。
例えば、ブラーンマナの家に生まれても、商業的な活動に専念するならその性質はヴァイシャであるとされます。
真のブラーンマナは、質素に暮らし、ヴェーダを学び教え、人々のために儀式を行う者です。
役割と性質は必ずしも一致しません。
役割としてヴェーダの儀式を行うブラーンマナが、実は名声や野心を求める性質を持っていることもあります。
しかし、もしその人が、カルマ・ヨーガの態度、つまり「これは私の役割であり、神への捧げものである」という考え方で役割を果たすならば、その人の性質は真にサットヴァ-ラジャス-タマスです。
この体系は、社会に存在する役割と、その役割を担う人々の本質的な資質の両面から、人間の分類を説明しています。