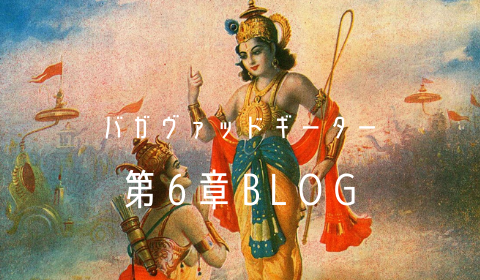
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।
yuktāhāravihārasya yuktaceṣṭasya karmasu |
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥६.१७॥
yuktasvapnāvabodhasya yogo bhavati duḥkhahā ||6.17||
食事やその他の活動を思慮深く適切に行う人
すべきこと、睡眠と目覚めの時間に関して適切に努力をする人
(その人にとって)瞑想は悲しみを破壊する道具となります
-
この詩は、瞑想に必要となる資質について述べます。
活動をする上で、適切・適度であることを意味する言葉が、ユクタ。
食事や、他の活動が、適切、適度である人が、ユクタ・アーハーラ・ヴィハーラ。
活動が、適切、適度である人が、ユクタ・チェーシュタ。
睡眠と目覚めの時間が、適切、適度に配分されている人が、ユクタ・スヴァプナ・アヴァボーダです。
この人は、教養と自制のある生活をし、生活そのものがヨーガ、そのヨーガがサムサーラの悲しみを破壊します[ヨーゴー バヴァティ ドゥッカハー]。
シャンカラの解説では「アーフリヤテー イティ アーハーラハ」と言われます。
食事[アーハーラ]・他の活動[ヴィハーラ]が、適切で、活動を均整のとれた感覚で行える人、行いに関する強迫観念や、妄想を制御できる様な人が、ユクタ・アーハーラ・ヴィハーラです。
例えば、多くの時間を食事の計画に費やしたり、食事[アーハーラ]が、生きがいにさえなりますし、運動が生きがいになる人もいて、毎日、何時間もエアロビクスをし、ジャンクフードばかり食べて、それを体から出すことに、取り付かれているかもしれません。
エアロビクスが、生きがい、信仰になり、運動し、疲れきって、結局食べて寝てを毎日繰り返す様に、人生が運動することだけに費やされるべきでもありません。
均整のとれた感覚がなければ、アーハーラも、ヴィハーラも、虜にしてしまうので、クリシュナは、どんな活動もユクタでなければならないと言います。
食事を適切に摂ることがスピリチュアル、と考える人もいて、何を食べるか、どれだけ食べるかが強迫観念になりえますが、適切に食べることは、健康の為で、それ以上ではありません。
適切な食習慣に従い、毎日、運動したとて、泥棒や、鬼の様な人は、残虐な行いを遂行したり、罪を犯しますから、全てにおいて均整のとれた感覚を持つユクタは、ここで重要な言葉なのです。
ユクタ・チェーシュタは、すべき事が沢山あったとしても、あらゆる行いに関して[カルマス]、苛々したりせず、時間を無駄にせず、一つ一つ注意深く、思慮深く、効率よく行います。
チェーシュタとは、手足の動きも含めて、あらゆる動きのことを意味しますから、ユクタ・チェーシュタは、様々な活動において、手足の動きに無駄がない人なのです。
一度に多くのことをしても、結果的には、何も出来ていません。
何かしたいと思っていたのに、急に何か他のことを思い出し、今していることを止めて、他のことをはじめ、また別のことを思い出し、手を止め、また次のことをする人は、アユクタ・チェーシュタです。
手の動きと向き合う瞑想をする、禅師の暮らしまでの必要はなく、大事なことは、全ての活動の中に、バランス感覚が必要であり、捉われないことです。
強迫観念からは、何も得られませんが、していることに注意を向けていることで、目覚めた(注意深い)感覚を得ることが出来ます。
ユクタという言葉は、していることに注意を向け、なすべきことをする、ということです。
知識を得ることを可能にする、内側のゆとりがそこにあるのです。
この詩で扱われている人は、眠りや、起きている時間に関して、均整の取れた感覚がある人です[ユクタ・スヴァプナ・アヴァボーダ]。
子供時代の睡眠時間や、体質を含む様々な要因で、人それぞれ、規定はないので、ユクタという言葉が、慎重に使われていることを理解します。
睡眠や起きている時間のバランス感覚のある人に、ヨーガはあります[ヨーガハ バヴァティ]。
このヨーガは、悲しみを打ち砕く[ドゥッカハー]知識です。
この知識は、悲しみにさらされている人の世界観の全てを変容させることで、悲しみを打ち砕くのです。
世界観の変容とは、自己理解、私は悲しみから自由であると見抜くこと[バーディタ・アハンカーラ]を意味します。
行い手を否定し、悲しみが上手く対処されます。
この様に、悲しみの破壊(人の根底の問題の消散)は、純粋に知識[ニャーナ]を意味し、この知識をここでヨーガと呼んでいます。
シャンカラの解説でドゥッカは、あらゆる種類の悲しみ[サルヴァ・サムサーラ・ドゥッカ]を指しています。
「私の人生は大丈夫、私の周りの人が問題」と言うのは、人生が大丈夫ではないことを示しています。
ですから、全ての悲しみを破壊する知識の追求に人生を注ぎます。
食べ過ぎず、食べなさすぎず、眠り過ぎず、睡眠不足にならず、運動し過ぎず、また全く運動をしないことなど、ありませんように。
すなわち、行いをゴールとするのではなく、それを手段とし、行いをカルマヨーガに還します。
生活の中に、教養と鍛錬を持つには、適切、適度な釣り合いが必要です。
例えば、ヨーガ・アーサナなどは鍛錬で役立ちますが、その練習だけに生活を専念させることでも、無視するということでもありません。
探求者は、アシュターンガ・ヨーガに基づくある規律に従うので、瞑想的な生活は、ヨーガ・アーサナとプラーナーヤーマを含みます。
従うべき規律も、適切、適度なバランスを保つ、つまり、熱中しすぎないし、無視されないことが重要です。
取り組むことが、その人にとって生きがいになってしまう傾向が多々あります。
するよりむしろ、知るべきことがある、ので熱狂者になるべきではない、とクリシュナは言います。
人の体[シャリーラ]は、モークシャを得るための基本となる道具[サーダナ]として、カーリダーサによって定義されました。
ユクタ・チェーシュタは、自分自身の知識を得ることを可能にするに必要な健康を享受するため、食べること、眠ること、適切な鍛錬など、適切な健康を維持し、これらを軽視せず、すべきことをします。
サムサーリーはいつも「いつ?」と言い、時間がかかること、骨の折れる追求は、本当に時間をかけるべきなのか?努力するに値するか?と、取り組む前から知りたがります。
しかし私は、既に自分自身を得ています。
私はあるがままで、あらゆる制限から自由であるという理解ですから、他に何も得るものなど無いのです。
「分かりました。完全な自己受容、私は全体という視点は、興味深いですが、いつこの世界観を得れますか? どの位かかりますか? それを早く得て、今まで通りの生活に戻りたいです。」
と、インスタントに学びたがるかもしれませんが、これは人生です。
「いつ?」はなく、そこには、ただ人生があるだけで、これ以外の人生はありません。
知っていようがいまいが、人が求めるものは、あらゆる制限からの自由。
何かをしたとて、この追求が失せることはありません。
どこにいても、何をしていても、自分自身と在りますから、それが十分な材料となり、この知識への明確さが増していきます。
それなりの時間は必要ですが、どこまでも喜びですから、それは問題ではありません。
煩わしさを感じる時に「これを、どれ位するのか?」と、気がかりになるのです。
自己の知識の追求は、自分自身の知識[アートマ・ヴィッデャー]、私の素晴らしさを教える知識ですから、いつもご機嫌です。
宗教は普通、あなたが、いかにひどい状況で、救われなければならないと説き(前半のヴェーダ)、これ(ヴェーダーンタ)を教えてくれません。
この知識は、既に私は救われていることを教え、そこには問題が無いので「いつ?」という質問は起こりません(10人目の男)。
しかし、知るべきことは、この知識を持つ人の状態ですから、それが次の詩で述べられます。
