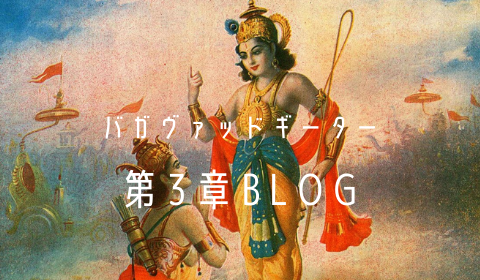
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
śreyānsvadharmo viguṇaḥ paradharmātsvanuṣṭhitāt |
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥३.३५॥
svadharme nidhanaṃ śreyaḥ paradharmo bhayāvahaḥ ||3.35||
他の人のダルマを上手に行うより、自分自身のダルマを不完全でも行う方がむしろ良い
自分自身のダルマの中での死がより良いのです。他のダルマは恐れをもたらします[35]
-
形、音、臭い、味などの感覚器官の対象物は、好きなもの、そうではないものがあります。
様々な形の欲求で、自分の考えにこれらの好き嫌いが起こりますが、それは習性[プラクルティ]であり、イーシュワラです。
私は体験者、行い手という観念、自由意思があるところに、シャーストラが働きます。
ダルマとアダルマ、更にサッテャとミッテャーを、シャーストラは扱いますが、アルタ・カーマを求めるのか、価値構造が整いモークシャを求めるかは、人それぞれです。
習性はコントロール不可能と、前の詩で言われたからと言って、にシャーストラは役に立たないと考えることはできません。
性質[プラクルティ]は、ラーガ・ドヴェーシャとして現れる思考の形で、それに沿って進むかどうかは、私の自由意志に完全に依存しています。
役に立つことを求める生き方(実用主義)、自分の良心から善悪を行わない(道徳)、ダルマとアダルマの確かな基準も考慮に入れられるべきです。
◎道徳的な人がいつもカルマ・ヨーギーだとは言えない
行いの選択にイーシュワラへの気付きがあるなら、それはカルマ・ヨーガですが、イーシュワラへの気付きがないなら、それは成熟した人の選択です。
「私がキリスト教徒ではない理由」という本の著者バートランド ラッセルは、原子爆弾の激増に反対の声を上げた最初の人で、彼はどの様な宗教も持たない偉大な道徳をわきまえた人した。
ある程度、視野の広い人なら誰もが道徳を理解します。
他者が、どの様に振舞ってくれると嬉しいか、また逆に、他者が同じことを期待していることも人は知っています。
ですから道徳は、一般常識で、ある程度成熟があれば、より鮮明に理解され得るものです。
道徳的な人であるために、聖典の申し付けや宗教観は必要としませんが、世界の宗教聖典は、道徳的な価値に何かを付け加え、プンニャとパーパの概念などが入ってきます。
しかし、単に何が道徳的で、何が非道徳的かを理解するのに、宗教は必要ありませんから、人はカルマ・ヨーギーでなくても道徳的であり得ます。
イーシュワラが、行いの結果を与える人[カルマ・ パラ・ダーター]という理解があれば、その人はカルマ・ヨーギーです。
カルマ・ヨーギーは、帰依者[バクタ]ですから、「これは私の物」という認識ではなく、肉体も、考えも、世界も、 好機も、資源、技術時間、場所、全てが与えられていると理解します。
そして、その背後には、与える人がいることを理解している人にカルマ・ヨーガがあります。
今、この瞬間、この場所ですべき事と、したい事がたまたま一致するなら、行いは自動的です。
また、すべきでない事が、したくない事であるなら、その行いを避ける事も自然に起こるのです。
◎自動的な行い
カルマヨーギーは、ラーガ・ドヴェーシャはありますが、ダルマと調和していますから、自動的に反応し、何にも摩擦しませんし、法則は摩擦されません。
しかし、ラーガ・ドヴェーシャが、ダルマ・アダルマと一致しないなら摩擦があります。
これが「自分自身のダルマの中での死がより良い。他の人のダルマは恐れをはらむ[スヴァダルメー ニダナム シュレーヤハ パラダルモーバヤーヴァハハ」とクリシュナ神が言う理由です。
私の選択は、行いに関してだけで、考えに何がポップアップするかには、選択はありません。
スヴァ・ダルマは、その人自身によってなされねばならない事で、ここではダルマはカルマを意味しています。
イーシュワラの視点からは、ダルマとは秩序、ダルマの法則で、個の視点からは、その法則は、行い[カルマ]の結果が返ってくるものですから、ダルマとカルマはコインの裏表のようなものと言われます。
ヴェーダの文化では、社会を構成する4つの家柄[ヴァルナ]と、人生の4つのステージ[アーシュラマ]がありました。
受け継がれる家柄の仕事を大切にしながら、その人生のステージで、すべきことをする。
競争社会ではなく、お互いが助け合いながら、自分自身の成熟にコミットできる完璧なシステムでした。
このシステムは、現在は働いてはいませんが、明らかな事は、どんな状況においても、その状況が私に求めている行いがあり、それに応えることが私の義務だということです。
義務とは、誰かに言われなければならない何かではなく、自分の置かれている状況を、あるがままに理解するなら、それは明らかなのです。
もし、自分自身の置かれている状況が理解できないなら、自分自身の義務[スヴァダルマ]が何かを理解するために、より視野が広く、利害関係のない人に相談することができます。
また、この詩のスヴァダルマの概念、その意図を理解する必要があります。
それが上手にできるか、どうかではなく、その過程で滅亡したとしても、個人の立場おいて、なさねばならないことです。
機械のボルトの仕事は、しっかり留まることですが、ボルトがピストンのように動こうとするなら、機械全体が止まってしまいます。
サッカーのゴールキーパーは、2つのポストの間に立つことが役割ですから、他の選手と同じように、ボールを追いかけ走りまわるなら、それは大参事です。
あるべき仕組みの中で、すべきことをするのです。
それぞれの人が、与えられた状況の中で行うそれぞれの義務があり、その義務は、ただ為されねばなりません。
自分にとってメリットがあり、より好ましいことと言い、何か他の事をするより、自分自身の持ち場を守り、死ぬ事がより良いのです。
役割を変えたとて、自分が満たされることはなく、行いで自分が満たされようとするなれば、自分自身は足りてない人、という見方は強まります。
気づいていようといまいと、この制限からの自由[モークシャ]を求めています。
どんな役割であろうと、どんな仕事をしていようと、既に私はモークシャなのです。
◎スヴァダルマと満足
他者がしていることが、幸せそうに見える時、自分もそれをしたいと思いますが、スヴァダルマはそれではうまくいきません。
与えられたあらゆる状況で、それがどんな立場であっても、為されねばならない事が、カルマであり、ダルマです。
仕事を変えるべきではない、と言っているのではありません。
お金と仕事が満たされていることは重要ですが、それ以外の要因が考慮されなければなりません。
この詩で、他者の義務を自分自身のものとして取るなら、それは明らかに恐れをはらんでいる[バヤーヴァハハ]とクリシュナは言いました。
死ぬ事になろうとも、他者の義務をするよりは、スヴァダルマを果たす事、正しく適切な事を何であれする事がより良いのです。
もし自分自身の義務を怠って他に何かをするなら、葛藤し、後悔し、しなかった事、してしまった事の罪悪感を持つでしょう。
しなければならなかった事が、なされず、すべきでなかった事がなされるなら、これら全てが、生きながらの死です。
◎あなたの選択の練習
ラーガ・ドヴェーシャが考えに起こるなら、それをただ眺める練習をします。
それを受け入れ、眺める練習をするなら、それに沿って進まない事を選択することが次第にできてきます。
スヴァダルマが、魅惑的で、喜ばしく、魅力的で、満足させるような特色が無いもの[ヴィグナ]だとしても、自分自身の義務をすることが、他の人のダルマをするより明らかに良いのです。
常に、自分のすべきことがあり、ダルマは現れていますから、一人ひとりが、それをします。
ネジが、エンジンという全体の秩序を見るように、自分のカルマがヤッニャになることを理解します。
様々に現れる力を、単なる物としての力ではなく、イーシュワラの側面や特徴の数々[デーヴァター]として理解します。
太陽[スーリヤ]は、単なる爆縮ではなく、神からの恵みです。
太陽と地球が、見事な距離感を保っているのは明らかに神からの恵みです!
朝日が昇ることも、太陽系全体の中心として、全てにおいてそれは祝福、それは知識[イーシュワラ]です。
空気も、水も、大地も、全ての植物、虫などが神の恵み、デーヴァターとして尊敬され得る力だという理解があるなら、「〇〇すべきだ」と言う必要などなく、すべては自発的です。
視野を広げ、日本人として、妻として、母として、今置かれた役割を全うし、自分がしてほしいことを他者に自然と振る舞えるようになります。
あふれるイーシュワラを個の私がとめませんように、と祈ることが出来ます。
仲間や、他の生き物たちを理解する、この感受性を持つなら、他の動植物の必要性を理解するように言われたり、他者が期待する事をするようにと言われる必要もありません。
デーヴァターへの認識するなら、他の全てが含まれます。
◎傷つけるべきでない[アヒムサー]という行いの基準
1本の樹を切るなら、10本の樹を植えて世話をすべきであるとダルマ・シャーストラは言います。
このルールの背景にある考え方は、樹を切る事は、傷つける行為[ヒムサー]であるということです。
必要があるなら、樹を切っても良いのですが、同時に樹や、他の生き物に対して、傷つけるべきでない[アヒムサー]という気付きがあるべきです。
ジャイナ教の教祖マハーヴィーラは、アヒムサーを大切なものとして取り上げ、可能な限り、優しく傷つけないように、羽のほうきで道の虫たちを掃いたり、虫が口に入り、殺されることが無いよう、マスクをしたりします。
注意深く、虫に配慮し、歩く前にその道を掃くような感受性が豊かな人が、仲間である人間を殺す事などできません。
アヒムサーという行動基準で得る感受性の先にモークシャがあるのです。
ヴァルナとアーシュラマに従ったヴェーダの文化には、義務だけがありました。
「その人自身のダルマを行って死ぬ事がより良い[スヴァダルメー ニダナム シュレーヤハ]」
クリシュナがここで伝えたい意図は、この文化の真髄でした。
◎人がダルマを放棄する結果
儀式や宗教上の義務を執り行う役割を持つ[ブラーンマナ]は、社会の幸福を祈る事に伴い、ただ前半のヴェーダを学び教えることです。
それがすべき事なのですが、報酬が基準になるなら、モークシャへの価値が薄れます。
多くのブラーンマナ達がスヴァダルマを放棄し、エンジニアや医者や実業家や軍人という、耳を疑うような仕事を選んでしまうのです。
目的がモークシャなら、どの様な職種なのかは重要ではなく、イーシュワラを知る喜び、全てはイーシュワラからのお下がり、という考え方があるので、自分の仕事、置かれた環境を受け入れます。
自分がすべきことをして、考えが成熟することを知っているからです。
◎義務と権利は同じ1つのもの
権力とお金が基準になるなら、全ての考え方が変わります。
しかし、アンタッ・カラナ・シュッディが目的なら、職種が何なのかではなく、自分の仕事を全うすることを重要視します。
今日では、権利ばかりを主張し、責任を果たさないことが多々見られますが、ヴェーダの社会では、義務だけがあり、権利を主張したりしません。
学生の義務、夫の義務、王様の義務、全ての義務は、相互に関係しあっているのです。
神々[デーヴァター]や、先祖、家族、仲間、全ての生きもの対しての義務の数々の繋がる輪があります。
どの役割も脚本があり、それがスヴァダルマなのです。
夫としての脚本、スヴァダルマに従い、その人は義務を行うので、妻がある種の権利を受けます。
一市民として義務を行い、国もまたその義務を行い、それが市民の権利となり、市民の義務は国の権利となるのです。
ですから、ヴェーダの文化では義務しかなく、権利は、自然の結果としてもたらされるものです。
権利を命じたり、要求したりせず、義務を全うします。
ラーガ・ドヴェーシャを脇に置いて、すべきことをする時、アンタッ・カラナ・シュッディが可能です。
全ての人がそれぞれの権利を受け、争いがありません。
権利を主張する時、いつも戦いがあります。
「これは私の権利だ」と誰かが言うなら、他の人も同じことを言います。
「これは私の義務だ」と言いながら、どちらの人も戦うことはないのです。
◎義務には欲求がない
権利が力説される時、いつも要求の要因があり、要求がある所ではどこでも、拒否や要求し返すという事態が当然ありますから、摩擦や衝突が、いつもあります。
人々が常に要求するなら、社会は当然ながら要求社会となるのです。
個人だけではなく、民族、男性、女性、国家といったグループまでが要求します。
しかし、義務には欲求はありません。
お互い協力しあうこと、仲間を理解しています。
自分自身の義務を完全に満たすことなどできないので、謙虚さがあるのです。
これが、人間のダルマ[マーヌシャ・ダルマ]なのです。
家庭 、共同体、社会、世界で、人々が共に生きるには、これが唯一の方法で、他の方法はありません。
シャーストラは、更に全ての自然の力も考慮に入れる様に言うのです。
この様に、他の人のダルマに従うのでなく、自分自身のダルマに従うこと[スヴァダルマ・アヌシュターナ]が、まさにカルマ・ヨーガの基盤です。
理解するなら、このヴェーダのヴァルナ、アーシュラマは、本当に美しい宇宙観です。
デーヴァターに感謝し、義務を果たすことまで視野を広げられ、そのことを思い出すことが祈りであり瞑想です。
